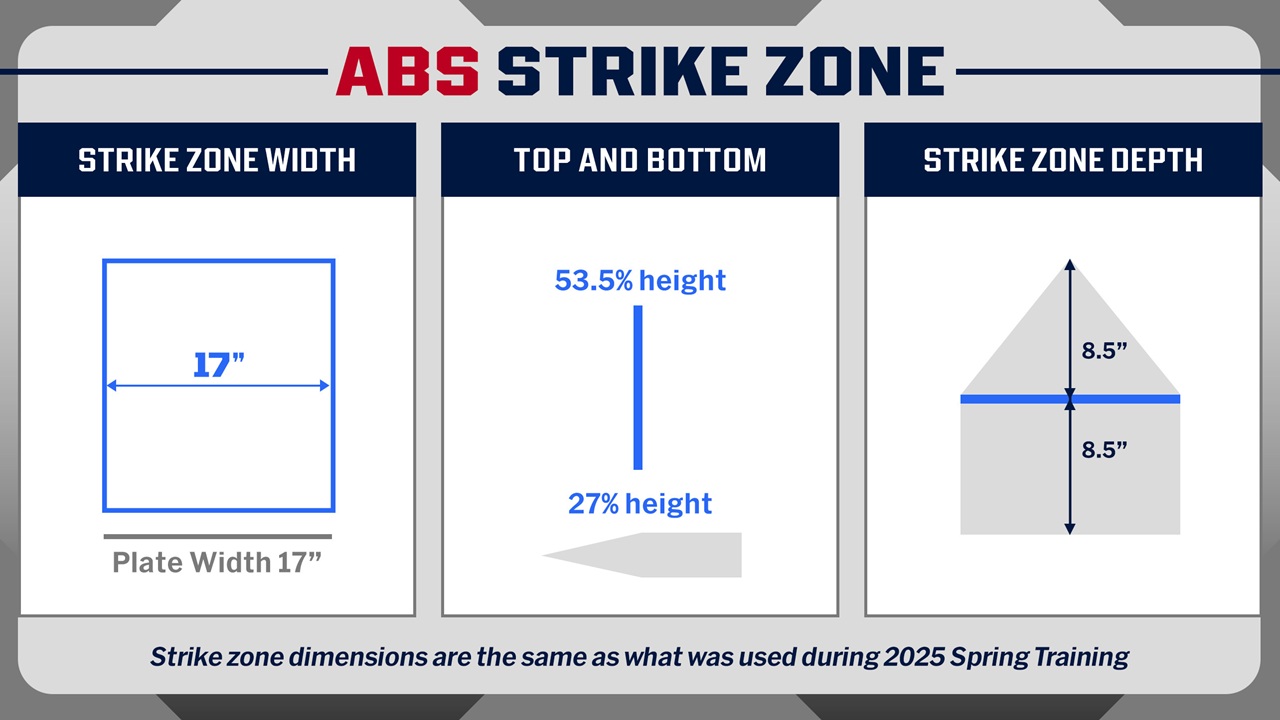勝負の分かれ目:フィリーズの九回の犠打は正しかったのか
2025.10.7 15:27 Tuesday
【フィリーズ3-4ドジャース】フィラデルフィア/シチズンズバンクパーク、10月6日(日本時間7日)
試合の趨勢(すうせい)だけではなく、シリーズの趨勢を決めた采配だったかもしれない。ナ・リーグ地区シリーズ(NLDS=5回戦制)の第2戦、4点ビハインドで最後の攻撃を迎えたフィリーズは、起死回生の逆転劇の一歩手前に迫っていた。
先頭からの3連打で瞬く間に2点を奪い、3-4と1点差に迫り、なおも無死二塁の好機。たまらず切り札の左腕ベシアを投入したドジャースに対し、フィリーズは代打から登場していた7番の左打者ストットが打席に入った。
ストットは送りバントを試みたが、ドジャースの三塁手マンシーの好フィールディングに阻まれ、二塁走者カステヤノスが三塁でタッチアウト。犠打は失敗したものの、1死一塁となり、その後代打ベイダーの単打でフィリーズはチャンスを広げた。しかし、あと1本が出ず、4-3で敗戦。シリーズは0勝2敗となり、シーズン終了のがけっぷちに追い込まれた。
“たられば”を言っても仕方がない。しかし、ストットが送りバントを成功させていれば、あるいはそもそも試みていなければ、試合の結果は変わっていたかもしれない。仮に送りバントが成功ないし二塁走者が三塁でアウトになっていなければ、後続のベイダーが左中間に放った単打で同点の走者が生還していた可能性は高いだろう。
近年、データ分析が進んだ野球の世界では、送りバントは非効率であるというのは常識になりつつある。しかし、どうしても1点が欲しい終盤の場面(特に1点が勝負とシーズンの成否を決するポストシーズン)では、MLBでも送りバントが行われることは珍しくない。
ただ、やはりデータはストットの送りバントの判断に疑問符を突きつけている。
MLBのデータアナリストであるトム・タンゴ氏は試合後、自身のXでストットの送りバントが変動させた試合の勝利確率のデータをポストした。
仮に送りバントが成功して1死三塁となっていた場合でも、フィリーズの勝利確率は2%低下していた。しかし、仮に打者走者も生きるバントで無死一、三塁となっていた場合は、勝利確率は20%上昇していた。一方で、送りバントが失敗して1死一塁となった場合は、勝利確率が20%低下する計算だった。フィリーズは最悪の結果を引き当ててしまった。
なぜフィリーズ(あるいはストット)は送りバントを試みたのだろうか。
まず打席に入っていたストットは、左腕に弱い。左腕に対する今季のOPSは.575と、右腕に対する.760と比べて大幅に悪化する。そもそも左腕スネルが先発するこの試合では先発から外れ、代わりに右打者のソーサがスタメンに入っていた(よってこの終盤で右打者を代打に送る選択肢は最初からなかった)。
ただ、走者2塁の局面ならば、左打者は引っ張った内野ゴロあるいはライトへの十分な飛距離のある外野フライでも走者を進塁させることができる。しかし、フィリーズは送りバントのサインを出さなければ、走者を進めることも難しいと判断したのかもしれない。
事実、相対したベシアは進塁打に適した内野ゴロやフライを打つのも容易くない好投手だ。浮き上がるようなフォーシームを武器とし、三振とフライの割合が非常に高い。データサイト「ファングラフス」によれば、ベシアのフライ率は54.0%でMLB9位、そして内野フライ率22.1%でMLB2位(ともに50イニング以上)にランクインしている。
また、ストットはベシアに対して通算5打数無安打と相性も悪かった。2022年、2023年、そして今季の3シーズンで7打席対戦し、2四球を選んだが、2三振を喫した。残り3度の凡退では、1度は右中間への大飛球があったものの、残り2度は犠牲フライには足りない平凡な外野フライに打ち取られた。
仮にストットが走者を動かせずに凡退し、1死二塁になっていた場合の勝利確率は16%減の27.8%だった。フィリーズは1死二塁になるリスクを嫌い、成功しても勝利確率が2%微減する送りバントに踏み切ったということになる。
あるいは、送りバントをする前に別の采配のカードを切るべきだったという指摘もあり得る。それが二塁走者カステヤノスへの代走だ。カステヤノスのスプリントスピードは平均をかろうじて上回るレベルだが、「スタットキャスト」の走塁得点指標(「ベースランニングバリュー」)では通算-13と、走塁が上手い選手ではない。
送りバントで三塁タッチアウトになった走塁も、スタートが良かったとは言えず、走塁の上手い走者であればセーフになっていた可能性もあったかもしれない。さらに、仮に送りバントが成功して1死三塁になっていた場合でも、カステヤノスが際どい内野ゴロや外野フライで生還できたかには疑問が残る。
しかし、フィリーズには代走の選択肢がなかった。この日ベンチスタートだった5選手のうち、ストットを含む2人が既に途中出場済み。九回の時点では唯一の控え捕手マーチャンを除き、2人の選手しかベンチに残っていなかった。ただ、そのうちの一人のベイダーは第1戦で足を負傷して途中交代しており、この日も代打で安打を放ったあとすぐに代走を送られている。負傷で走れないベイダーがサヨナラの走者として出塁した場合に備え、代走を残しておく必要があった(さらに仮に延長戦に突入した場合、ベイダーへの交代枠がなければDHのシュワーバーを守備に出さなければいけなかっただろう)。
現代野球では、送りバントはほとんどのシチュエーションで非効率な戦略とされる。この日、九回無死2塁の好機を迎えたフィリーズにとっても、バントの判断は正しくなかったかもしれない。しかし、それを承知の上でフィリーズが送りバントに踏み切った要素も複数考えられる。
結局は三塁からの猛チャージでバントを処理した三塁手マンシー、二塁の牽制カバーからダッシュで三塁に入ってタッグプレーを成立させた遊撃手ベッツ、そして絶体絶命の窮地に陥りながらもベシア(そして佐々木朗希)へとつなぐ余力を残していたドジャースが一枚上手だったということかもしれない。フィリーズにとっては痛恨の惜敗となった。