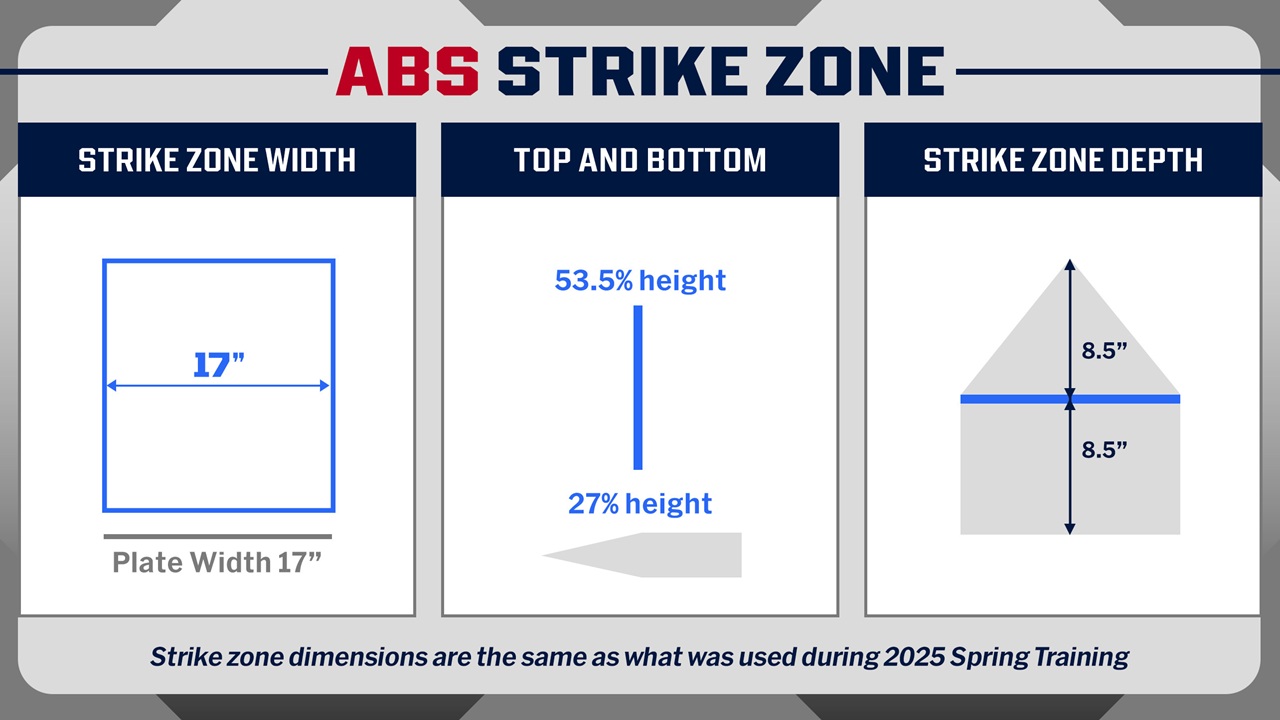スイーパーの流行から2年後、新たなトレンドとは?
2025.11.23 18:39 Sunday
2023年のワールドベースボールクラシック(WBC)決勝の最終打席、今でも語り草となっている大谷翔平とマイク・トラウトの名勝負は、大谷の鋭く曲がるスイーパーにトラウトのバットが空を切り、空振り三振で決着した。その名勝負が大きな契機となり、スイーパーはトレンドの球種として持て囃されるようになった。
しかし、それから2年後、早くもスイーパーは「トレンドの球種」ではもはやなくなっている。スイーパーに代わる新たな投打のトレンドとは何だろうか。
2022年の黄金期からわずか数年で衰退
大谷がスイーパーでWBC優勝を決める前年の2022年は、まさにスイーパーにとって黄金期だった。スイーパーに分類される大きなスライダーは前年から倍増して28360球を投じられ、被打率はわずか.194。さらに、1球単位で失点をどれだけ増減させたかを示すピッチャー・ラン・バリュー(状況ごとの重み付けなし)という指標では、スイーパーは全体の4.0%の割合でしか投げられていなかったにもかかわらず、+104を叩き出し、さらに100球あたりのラン・バリューでも0.366(ともに主要球種中2位)を記録した。
しかし、2022年を境にスイーパーは打者に適応されていった。翌2023年はスイーパーの存在がより一般的になり、投球数が42001球に達したが、ラン・バリューはむしろ減って+57(100球あたりでも.136)。2024年も投球数は48020球が投じられたが、ラン・バリューは+42(100球あたりでは.088)に低迷した。
そして2025年は投球数の増加が49534球と頭打ちになり、ラン・バリューは+7、100球あたりでも.014と一気に落ち込んだ。
わずか3年前には球界を席巻していたはずのこの球種に一体何があったのだろうか?
「引っ張りフライボール革命」が打者側の新たなトレンドに
スイーパーが投手側のトレンドとして大流行した一方、打者側では「“引っ張り”フライボール革命」とでも言うべき、新たなトレンドが生まれていた。
「フライボール革命」といえば、2010年代半ばのMLBを席巻したことで聞き覚えのある人も多いだろう。簡潔に表現するならば、フライを打ち上げる方が効率的に得点を生み出せるという考え方のことで、これを大いに取り入れたアストロズなどが大成功を収めたことで、一躍脚光を浴びた。スイーパーの台頭も、「フライボール革命」をも含む大きなトレンドの変遷の一部と言っても良く、「フライボール革命」の考え方は現代野球の基本にもなっている。
そして今、「“引っ張り”フライボール革命」とでも言うべき潮流がMLBでは見られている。従来、引っ張り一辺倒になるのは良しとされておらず、広角にフィールド全体を使い、センター返し・流し打ちできる技術を持つ打者こそ良い打者であるという価値観が主流だった。
しかし、今は違う。他のどの打球分類よりも「引っ張り方向」の「フライ打球」が良い結果に結びつくということがデータで示され、広角に打ち分けずとも正確無比に「引っ張り方向のフライ」を打ち続ける打者も評価されるようになってきた。
「引っ張りフライ」は、打球全体のうち17.5%の割合でしか発生していないものの、ホームラン全体の66%を占めていた。バックスクリーンへの一発がパワーの証、逆方向へのホームランが技術とパワーの結晶と特別に扱われることが多々ある通り、基本的に引っ張ったホームランが多いという事実は頷ける。
従来の野球観において、引っ張り一辺倒の打撃やプルヒッターが批判されていたのは、それによって大振りになってしまい、確実性が下がってしまうからという理由が大方を占めるだろう。
しかし、データによると、「引っ張りフライ」は確実性も上げてくれる。同じく2022-24年の期間において「引っ張ったフライ」は打率.547、長打率1.227、wOBA(攻撃力を測る指標で、出塁率と同じスケールで見ることができる)では.733と、驚異的な打撃結果を残していた。一方で、「引っ張りフライ」以外の打球分類では、打率.319、長打率.527、wOBA.353と格段に数字は落ちる。
「引っ張りフライ」の有効性は今や広く知れ渡っている。MLBでは2015年から「引っ張りフライ率(プル・エア%)」が上昇し続けており、2025年はスタットキャスト導入後では史上最高の18.2%に達した。
なぜ「引っ張りフライ」がより良い打球結果に結びつくのだろうか。
打球を引っ張るためには、ボールを前でさばかなければならない。そして、このボールを前でさばくことは、それ自体にメリットが詰まっている。
ボールを前でさばくことのメリットは、より速いスイングスピードが速い状態でバットがボールをとらえられることだ。当然ながら、よりスイングスピードが速い状態の方がパワーが生まれやすい。事実、打球を引っ張ったときのスイングスピードは、流し打ちしたときに比べておよそ4マイル(5キロ)も速いという。
実際、すべてのホームランの内、8割以上が前でさばいた結果、生み出されている。マイク・ペトリエロによれば、2024年のホームランの82%が、打者のスタンスの重心から25-45インチ(64-114センチ)前でバットとボールが当たっていた。大谷翔平(ドジャース)やアーロン・ジャッジ(ヤンキース)のように引き付けて逆方向にホームランを打てるパワーの持ち主は稀有であり、多くの打者がボールを前でさばくことでパワーを最大化しようとしている。
大激戦となった今年のワールドシリーズ第7戦でも、スイングスピードが平均以下のミゲル・ロハスとウィル・スミスが、お手本のような前でのさばきを見せ、戦局を変えるホームランを放ったのは記憶に新しい。
スイーパーは「引っ張りフライボール革命」の格好の餌食か?
ここまで、近年のMLBで見られる「引っ張りフライボール革命」について説明した。「引っ張りフライボール革命」の信奉者の打者が狙っているのは、投球を前でさばいて引っ張り方向にフライを打つこと。そして、「引っ張りフライボール革命」の少し前に台頭したスイーパーは、その格好の餌食となり得る性質を持つ。
スイーパーの「被引っ張りフライ率」は全球種中最多の25.7%。今季は2位のスライダーに3ポイントの差をつけ、最も危険とされる「引っ張りフライ」を浴びた球種となった。
とはいえ、スイーパーの「被引っ張りフライ率」は、本格的にスイーパーが投じられるようになった2021年から毎年主要球種の中でワーストを記録している。つまり、被引っ張りフライ率が高いせいでスイーパーが打たれるようになったと言えるわけではない。
実際にスイーパーが打たれるようになった理由は、打者の目が慣れ、適応してきたという点が大きいだろう。また、流行に乗ってスイーパーを投げる投手が増え、質の低いスイーパーが増えた可能性もある。打者はスイーパーを見極められるようになり、スイーパーに対するボール球スイング率は2021年の32.4%から年々低下し、今季はついに3割を割って29.9%になった。さらにスイーパーに対するスイングスピードは計測が始まった2023年から毎年上昇し、スイングスピードが75マイル(120キロ)を超えた割合を示すファスト・スイング率は2023年から約4ポイント増の23.0%へ。それらが要因となってか、冒頭で挙げたラン・バリューの低下に顕著なように、スイーパーは以前より打たれるようになった。
打者がスイーパーに適応してきた以上、スイーパーを多投するのは危険かもしれない。ましてやスイーパーは危険な引っ張りフライを浴びやすい性質を持っている。
投手は新たなトレンドを模索
一大トレンドとなったスイーパーに衰退の兆しが見えたとはいえ、それでMLBの投手たちが黙っているわけではない。投手たちは既に新たなトレンドを確立しつつある。
これまではスイーパーやそれ以前の高めのフォーシーム、フライボール革命で淘汰されたはずのシンカーの復権など、特定の球種がトレンドになってきた。
しかし、特定の球種がトレンドとなり、多くの投手がその球種を投げるようになれば、打者は目が慣れてすぐに適応してしまう。スイーパーに限らず、多くの変化球が年々攻略されている傾向にある。日本人投手の代名詞として絶大な威力を誇ったスプリットも、今季は2015年以降で最多の23596球が投じられたが、100球あたりのピッチャー・ラン・バリューは2016年以来の低水準となる.071と低迷。2022年には.476と絶大な有効性を示していたにもかかわらず、わずか数年で急降下した。
そこで生まれた新たなトレンドは「多くの球種を投げ分ける」というものだ。デービッド・アドラーによれば、スタットキャストが導入された2015年以降で、今季は「5球種以上投げた投手」あるいは「6球種以上投げた投手」の割合が過去最多だった。さらに注目すべきは、ただ多くの球種を持っているというだけではなく、多くの球種を均等に使い分けて打者を攻めている点だ。
多くの変化球を使い分けることで知られるダルビッシュ有は、このトレンドについて「自然な流れだと思う。今の打者は10年前よりも多くの球種を見ているからね。投球フォームを全て再現できるトラジェクト・アークのようなピッチングマシンも増えている。だから、私にとっては自然な進化だと思う。(球種の組み合わせを)打者に合わせて調整できる。小さなスライダーは打てるけど、大きなスイーパーは苦手という打者もいます。だから、全ての球種を揃えておけば、どんな打者にも対応できる」という旨のコメントを残している。
データ分析の進歩によって、日進月歩で戦略が進化するMLB。激しい力と力のぶつかり合いの裏には、投手と打者による終わりなきいたちごっこのような頭脳戦が隠されている。