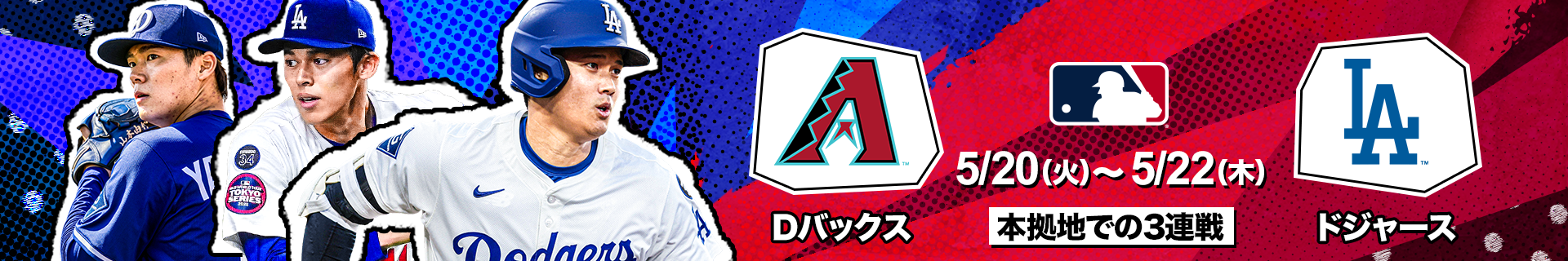【前半戦レビュー】ア・リーグ東部地区
2017.7.13 15:08 Thursday

2017年のレギュラーシーズンは前半戦が終了。試合が行われない今日、明日の2日間を利用して、全30球団の前半戦を簡単に振り返っていく。第1回はア・リーグ東部地区だ。
ボルティモア・オリオールズ(42勝46敗:地区4位)
先発防御率5.75は他球団に大差をつけてリーグワースト(14位ツインズは4.95)。ディラン・バンディ(8勝8敗、防御率4.33)が開幕から8先発連続でクオリティ・スタートを達成するなど健闘していたが、6月以降は息切れした。勝ち越している先発投手は一人もおらず、本格ブレイクが期待されたケビン・ゴーズマン(5勝7敗、防御率5.85)と4年連続2桁勝利のクリス・ティルマン(1勝5敗、防御率7.90)も期待外れ。守護神ザック・ブリットン(11試合、防御率2.25)が長期離脱する中、ブリットンに代わってクローザーを務めたブラッド・ブロック(38試合、防御率2.58)、セットアッパーのマイケル・ギブンス(37試合、防御率2.25)、左腕リチャード・ブライアー(25試合、防御率1.48)らが踏ん張ったものの、ブルペン陣の頑張りが無駄になる試合のほうが多かった。
打線はリーグ6位の123本塁打と相変わらずコンスタントに一発は出るものの、392得点はリーグ11位に過ぎず、出塁率.308はリーグ14位、18盗塁はリーグワーストと出塁や機動力を軽視したことが得点力の低下に繋がっている。オールスター初出場を果たしたジョナサン・スコープ(打率.295、18本塁打、OPS.883)と新人トレイ・マンシーニ(打率.312、14本塁打、OPS.892)の活躍が目立ったが、マニー・マチャド(打率.230、18本塁打、OPS.741)やマーク・トランボ(打率.254、14本塁打、OPS.738)のコンディションがなかなか上がらず、クリス・デービス(打率.226、14本塁打、OPS.781)は三振を量産した挙句、故障で長期離脱となった。
ワイルドカードを狙える位置にはいるものの、地区のレベルが高いのは大きなハンデ。先発ローテーションを立て直し、大雑把な攻撃を改善していかなければ、このままズルズルと負け越しの数を増やしていくだけになるだろう。
ボストン・レッドソックス(50勝39敗:地区1位)
防御率3.82はリーグ2位。デービッド・プライス(4勝2敗、防御率3.91)が故障で大きく出遅れるというアクシデントはあったものの、新加入のクリス・セール(11勝4敗、防御率2.75)が期待通りのピッチングを披露し、ドリュー・ポメランツ(9勝4敗、防御率3.60)も安定した活躍。昨季のサイ・ヤング賞投手であるリック・ポーセロ(4勝11敗、防御率4.75)には後半戦の奮起を期待したい。ブルペン陣ではクレイグ・キンブレル(36試合、防御率1.19)が完全復活して守護神と呼ぶに相応しいピッチングを続けており、ジョー・ケリー(34試合、防御率1.49)もリリーフ本格転向で開花。もう一人、頼れるリリーバーがいると台所事情はかなり楽になりそうだ。
打線はリーグワーストの92本塁打に終わるなどデービッド・オルティス引退の影響を感じさせたが、431得点はリーグ4位。極端な得点力不足には陥っていない。OPS.900以上のスラッガーは一人もいないが、70試合以上に出場した7選手がいずれもOPS.779以上をマークしており、OPS.800以上も4人。本塁打が少なくとも、ヒットを繋いで点が取れる打線になっている。ムーキー・ベッツ(打率.272、16本塁打、OPS.841)は爆発する試合と沈黙する試合の波が大きく、安定したパフォーマンスを求めたい。パブロ・サンドバル(打率.212、4本塁打、OPS.622)の不振と故障により三塁に大きな穴が開いており、トレード・デッドラインでの補強に動くことになりそうだ。
セールを獲得し、目標は地区優勝ではなくワールドシリーズ制覇だったはず。そのためには三塁手の補強はもちろん、ポーセロの復調、ベッツやザンダー・ボガーツ(打率.303、6本塁打、OPS.806)のもうワンランク上の活躍など、まだまだ足りない要素がある。
ニューヨーク・ヤンキース(52勝34敗:地区2位)
エース田中将大(7勝8敗、防御率5.47)の大不振、守護神アロルディス・チャップマン(23試合、防御率3.48)の故障離脱という誤算はあったものの、リーグ4位の防御率4.02は及第点。先発陣ではルイス・セベリーノ(5勝4敗、防御率3.54)が開花し、オールスターにも選出された。また、新人左腕ジョーダン・モンゴメリー(6勝4敗、防御率3.65)も期待以上のパフォーマンスを披露している。ブルペン陣はチャップマン離脱の穴を埋めるべく奮闘していたが、徐々に息切れ。チャップマンが本調子ではなく、28.1イニングで26四球を与えているデリン・ベタンセス(32試合、防御率3.18)の制球難も深刻だ。
打線は新星アーロン・ジャッジ(打率.329、30本塁打、OPS1.139)の活躍もあり、リーグ2位の477得点を叩き出した。スターリン・カストロ(打率.313、12本塁打、OPS.835)、マット・ホリデイ(打率.262、15本塁打、OPS.877)、アーロン・ヒックス(打率.290、10本塁打、OPS.913)といった打線を支えていた打者たちが次々に故障離脱し、6月以降は急失速してしまったが、ゲーリー・サンチェス(打率.276、13本塁打、OPS.850)やディディ・グレゴリウス(打率.291、10本塁打、OPS.779)もまずまずの成績を残しており、開幕前の評判を考えれば「期待以上」と言っても過言ではない。チームの足を引っ張っている一塁だけは、なるべく早く補強に動きたいところ。
次なる黄金期への「過渡期」と見られていた今季だが、途中まで地区首位を走る予想外の健闘。ただし、ジャッジがこのままのペースで突っ走るとは思えず、ポストシーズン進出のためには投打両面で戦力の底上げが不可欠だろう。
タンパベイ・レイズ(47勝43敗:地区3位)
マット・アンドリース(5勝1敗、防御率3.54)の長期離脱は大きな痛手だが、クリス・アーチャー(7勝5敗、防御率3.95)、アレックス・カッブ(7勝6敗、防御率3.75)に新人ジェイコブ・ファリア(4勝0敗、防御率2.11)が加わった先発ローテーションはなかなか強力。先発防御率4.05はリーグ2位であり、チームの強みとなっている。その一方でブルペン陣は苦戦気味。クローザーのアレックス・コロメイ(38試合、防御率3.76)には昨季のような安定感がなく、期待以上の活躍を見せているのはトミー・ハンター(29試合、防御率2.13)くらい。元クローザーのブラッド・ボックスバーガー(4試合、防御率0.00)がようやく戦列に復帰しており、コロメイの状態次第ではボックスバーガーとのダブル・クローザー体制の導入、あるいはクローザー交代も視野に入ってくるだろう。
打線はエバン・ロンゴリア(打率.259、12本塁打、OPS.744)が低調だが、ローガン・モリソン(打率.258、24本塁打、OPS.931)やコリー・ディッカーソン(打率.312、17本塁打、OPS.903)の活躍により133本塁打はリーグ3位、428得点はリーグ6位と長年の「投高打低」傾向を解消。マレックス・スミス(打率.333、1本塁打、OPS.828)、ティム・ベッカム(打率.274、11本塁打、OPS.760)ら伏兵も好成績を残している。新加入のウィルソン・ラモス(打率.242、3本塁打、OPS.873)が戦列復帰を果たし、長期離脱中のケビン・キアマイアー(打率.258、7本塁打、OPS.737)も後半戦のどこかのタイミングで復帰できるはず。さらなる得点力アップも期待できそうだ。
トレード・デッドラインで派手に動くチームではないが、先発投手陣が安定した投球を続け、それを打線がしっかり援護できれば、大型補強がなくとも、おのずと白星はついてくるはず。4年ぶりのポストシーズン進出を期待したい。
トロント・ブルージェイズ(41勝47敗:地区5位)
先発ローテーションの中で期待通りと言えるのはマーカス・ストローマン(9勝5敗、防御率3.28)だけ。他の4投手は故障や不振により、期待を下回るパフォーマンスに終始した。先発ローテーションの穴を埋めるためにジョー・ビアジーニ(2勝8敗1セーブ、防御率5.52)をブルペンから先発に回したが、11先発で防御率5.60と結果は今一つ。マイナーから登用された投手は揃って結果を残せなかった。ブルペン陣では守護神ロベルト・オスーナ(37試合、防御率2.06)と右腕ダニー・バーンズ(32試合、防御率2.31)が合格点のピッチング。しかし、救援防御率4.21はリーグ9位に過ぎず、安心して試合終盤を任せられるような状態ではなかった。
主力投手の故障や不振により戦力ダウンした先発投手陣と同様、打線もジョシュ・ドナルドソン(打率.261、9本塁打、OPS.868)の故障やホゼ・バティースタ(打率.234、14本塁打、OPS.749)の不振をカバーできる選手がおらず、366得点はリーグ14位と得点力不足に陥った。新加入のケンドリズ・モラレス(打率.252、16本塁打、OPS.754)も物足りない成績に終わる中、ジャスティン・スモーク(打率.294、23本塁打、OPS.936)のブレイクは数少ない光明。しかし、スモークもすでに30歳。打線全体の高齢化と選手層の薄さは明らかにチームにとってネガティブな要素となっている。
ポストシーズン進出を完全に諦めてしまうような成績ではないが、地区のレベルが高いこともあり、急激なチーム状態の向上がなければポストシーズン進出は期待薄。今後は主力と控えの格差、主力選手の高齢化といった課題を解決するべく動いていくことになるのではないだろうか。
関連ニュース
7月13日 【前半戦レビュー】ア・リーグ西部地区
7月13日 【前半戦レビュー】ア・リーグ中部地区
7月13日 【前半戦レビュー】ア・リーグ東部地区
7月13日 オールスター終了はトレード市場オープンの合図だ!
7月13日 前半戦を10のトピックで振り返る